| これまでに開催した学会 | |
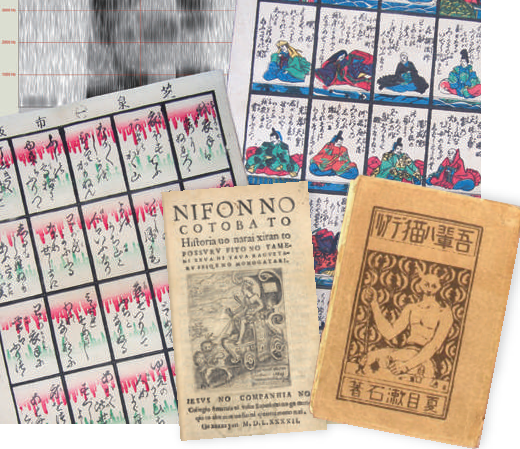 |
|
| 2025年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2026年1月10日(土) |
| 会場 | 福岡大学中央図書館1階 多目的ホール(ハイブリッド開催) |
| 研究発表 | 谷崎仁美「志賀直哉「⼩僧の神様」論」 |
| 研究発表 | 伊藤慶哉「林京⼦「トリニティからトリニティへ」論」 |
| 研究発表 | 于清川(ウ セイセン)「⻘来有⼀『爆⼼』論―時間について―」 |
| 講演 | ⼤関綾「〈しっぽく〉料理の表象―江⼾時代の⽂学作品における意味とイメージの変遷―」 |
| 2024年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2025年2月15日(土) |
| 会場 | 福岡大学AB01教室 |
| 研究発表 | 野口智代「戸澤正令の国学」 |
| 最終講義 | 高橋昌彦「全然、全集ではない!?」 |
| 最終講義 | 山縣浩「漂流50年」 |
| 2023年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2024年1月6日(土) |
| 会場 | 福岡大学中央図書館1階 多目的ホール(ハイブリッド開催) |
| 研究発表 | パトリック・パーマー「字形に基づいたイメージ・メタファー表現の考察」 |
| 講演 | 大坪亮介「(私的)『太平記』研究のこれまでとこれから」 |
| 講演 | 畑中 佳恵 「長崎イメージを追いかけて―研究テーマとの出会いを中心に― 」 |
| 2022年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2023年1月7日(土) |
| 会場 | 福岡大学A棟AB02教室(ハイブリッド開催) |
| 研究発表 | 竜口佐知子「宮沢賢治の「理想」について―「デクノボー」とグスコーブドリ」 |
| 講演 | 須藤圭「文学の可能性を問う―源氏物語の生成と享受―」 |
| 2021年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2022年2月26日(土) |
| 会場 | 福岡大学AB02教室(ハイブリッド開催) |
| 最終講義 | 國生雅子「〈子守唄〉考」 |
| 最終講義 | 山田洋嗣「近世末東海地方に於ける一好士の文芸生活」 |
| 講話 | 岡野ひさの「教員生活をふりかえって」 |
| 2020年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| ※中止(新型コロナウイルス感染防止のため) | |
| 2019年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2020年1月11日(土) |
| 会場 | 福岡大学AB01教室 |
| 研究発表 | 八木ゆかり「『源氏物語』の呼称―対の上の位置づけ―」 |
| 最終講義 | 田坂順子「九世紀の文学―都良香を中心に―」 |
| 2018年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2019年1月12日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 研究発表 | ジョユニ「芥川龍之介「毛利先生」論」 |
| 向井克年「ク語法研究の可能性―願望表現「見まく欲る」を中心に―」 | |
| 講演 | 林信蔵「私が考える比較文学の特徴とその役割」 |
| 2017年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2017年12月2日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 福岡大学日本語日本文学科三〇周年記念行事 先輩と語る | |
| 講演 | 原明子 |
| 武藤ゆう | |
| 末松久美 | |
| 徳永次郎 | |
| 2016年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2017年1月7日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 研究発表 | 八木ゆかり「『和漢朗詠集』四〇九「よそにのみ」の歌について」 |
| 向井克利「萬葉集における原因理由を表す助詞「カラニ」について」 | |
| 講演 | 佐野宏「萬葉集の表記体について」 |
| 2015年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2016年1月9日(土) |
| 会場 | 福岡大学AB02教室 |
| 研究発表 | 野田康文「井伏鱒二の〈国語〉学―「「槌ツァ」と「九郎治ツァン」はけんかして私は用語について煩悶すること」論―」 |
| 最終講義 | 大嶋仁「語ることの難しさについて」 |
| 2014年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2015年1月10日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 研究発表 | 馬場学「上代文献における「祈り」について―「鎮御魂斎戸祭」の解と併せて」 |
| 三嶋譲・有吉貴紀・武藤ゆう・宗新悟「芥川龍之介「文芸的な、あまりに文芸的な」注釈検討会―注釈の意義とその可能性―」 | |
| 講演 | 松本常彦「日本近代文学と夜の表象」 |
| 2013年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2014年1月11日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 研究発表 | 佐藤もも「日本語の音韻の第二言語習得に関わる要因―ベトナム北方方言話者の子音を中心に―」 |
| 阿比留章子「対馬藩宗家文庫について―文政年間を中心として―」 | |
| 2012年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2013年1月12日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 研究発表 | 園田克利「「ちかきふるうた」考」 |
| 竜口佐知子「『グスコーブドリの伝記』の結末を読む」 | |
| 講演 | 衣畑智秀「琉球語宮古島方言の終止連体形」 |
| 2011年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2012年1月7日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 研究発表 | 向井克年「コンナ類とコウイウ類の意味差― 対象の概括と例示を中心に―」 |
| 中野和典「空洞化する言説―井上光晴『西海原子力発電所』論」 | |
| 講演 | 中野三敏「和本リテラシーの回復を願って」 |
| 2010年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2011年1月8日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 研究発表 | 石橋剛「昭和三十年代における和田傳作品の研究」 |
| 黒木了二「夢野久作の宗教意識について」 | |
| 最終講義 | 三嶋譲「芥川龍之介・別れ」 |
| 2009年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2010年2月20日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 研究発表 | 向川克年「上代語副助詞「だに」「すら」について―「かくだにも」を中心に―」 |
| 鳥谷真紀「江戸川乱歩論「押絵と旅する男」を中心に」 | |
| 講演 | 小柳智一「未然形の向こう側」 |
| 2008年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2009年2月21日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 研究発表 | 山田裕介「「綺語抄」と平安時代の歌学」 |
| 武藤ゆう「遠藤周作における「疲れ」の表現」 | |
| 高橋敦「筒井康隆のドタバタ手法」 | |
| 講演 | 上野誠「折口信夫の挑戦― 「古代」を実感する方法を模索する」 |
| 2007年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2007年12月22日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 研究発表 | 有吉貴紀「日本近代文学史における宮澤賢治の位置を考えるために」 |
| 金銀英「日韓両言語間の翻訳方法について」 | |
| 講演 | 岡野ひさの「いわゆる逆説のノニは何を表すか」 |
| 2006年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2007年1月6日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 日本語日本文学科創設二十周年特別企画 | |
| シンポジウム | 「日本語日本文学研究の現在と未来」 司 会 大嶋仁 パネラー 佐野宏・長谷川薫・高橋昌彦・永井太郎・野田康文 |
| 2005年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2006年1月7日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 研究発表 | 幸克弥「林羅山の和学」 |
| 阿比留章子「男色大鑑の研究」 | |
| 最終講義 | 中野三敏 |
| 2004年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2004年11月27日(土) |
| 会場 | 福岡大学ヘリオスホール |
| 研究発表 | 冨永絵美「泉鏡花『註文帳』の空間構造」 |
| 長谷川英司「志賀直哉『母の死と新しい母』における表現の独創性」 | |
| 講演 | 田中道雄「俳諧雑談―芭蕉と蕪村をめぐって―」 |
| 2003年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2003年11月29日(土) |
| 会場 | 福岡大学A202教室 |
| 研究発表 | 金銀英「日韓における「気」の慣用表現の比較― 韓国語訳小説を中心に―」 |
| 高杉志緒「丹羽桃渓研究序論―伝記研究を中心に―」 | |
| 講演 | 杉村孝夫「日本語の地域的バリエーションー九州・琉球方言を中心として―」 |
| 2002年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2002年12月21日(土) |
| 会場 | 福岡大学ヘリオスホール |
| 研究発表 | 谷口佳代子「森鷗外「吃逆」論」 |
| 張翌彤「『小さき者へ』から『親子』ヘ」 | |
| 最終講義 | 秦行正「鷗外追尋」 |
| 2001年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2001年12月22日(土) |
| 会場 | 福岡大学AB01教室 |
| 研究発表 | 崔殷爀「杜甫詩の日中韓の解釈の違い」 |
| 舩越歩美「〈清〉の読みについて」 | |
| 最終講義 | 藤井茂利「二十一世紀の学問の方向」 |
| 2000年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2000年11月18日(土) |
| 会場 | 福岡大学A101教室 |
| 研究発表 | 崔殷爀「杜甫の詩の日本・韓国の解釈の相違」 |
| 真島玲子「源氏物語論」 | |
| 講演 | 中川成美「女流作家とジェンダー」 |
| 1999年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 2000年1月29日(土) |
| 会場 | 福岡大学ヘリオス・ホール |
| 研究発表 | 中野文仁「福岡方言の形容語」 |
| 野田康文「大岡昇平「野火」文体論序説」 | |
| 最終講義 | 清水孝純「漱石を読む―笑いのユートピアとしての「吾輩は猫である」―」 |
| 1998年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 1998年3月20日(土) |
| 会場 | 福岡大学ヘリオス・ホール |
| 研究発表 | 谷口佳代子「森鷗外「青年」論―情熱恋愛をめぐって―」 |
| 舩越歩美「古代日本語の形容詞「清」の世界」 | |
| 最終講義 | 白石悌三「「もがり笛」考」 |
| 1997年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 1997年11月22日(土) |
| 会場 | 福岡大学AB02教室 |
| 研究発表 | 長谷川薫「禁制詞「と思へば水の」考」 |
| 李知沫「古代日韓両国の模韻受容過程に於ける音韻史的考察」 | |
| 講演 | 迫野虔徳「「たそかれ」考」 |
| 1996年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 1996年11月23日(土) |
| 会場 | 福岡大学ヘリオスプラザ大ホール |
| 研究発表 | 張翌彤「「或る女」における時間と空間」 |
| 金東完「日本語教育を前提とした日韓両語の対照」 | |
| 講演 | 重松泰雄「漱石作品散歩―「道草」―」 |
| 1995年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 1995年11月11日(土) |
| 会場 | 福岡大学1011教室 |
| 研究発表 | 崔殷爀「韓国漢字音の頭子音脱落現象について」 |
| 酒井美和「山東京伝読本作品における″悪女″考」 | |
| 講演 | 板坂燿子「濡衣願望の世界」 |
| 1994年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 1994年11月19日(土) |
| 会場 | 福岡大学842教室 |
| 研究発表 | 盧善影「韓国漢字音と日本漢字音」 |
| 菊地由夏「「川端康成と古賀春江」 | |
| 講演 | 田所光男「比較文学概論補遺」 |
| 1993年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 1993年12月23日(土) |
| 会場 | 福岡大学842教室 |
| 最終講義 | 重松泰雄 |
| 1992年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 1992年9月28日(土) |
| 会場 | 福岡大学文系センター棟第四会議室 |
| 講演 | 李鍾徹「万葉集歌と郷歌の表記法」 |
| 1991年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 1992年1月9日(土) |
| 会場 | 福岡大学文系センター棟第四会議室 |
| 研究発表 | 新徳美穂「『今昔物語集』の一考察―女性をめぐって―」 |
| 亀井紀子「三島由紀夫「愛の渇き」―三郎殺しが問いかけるもの―」 | |
| 講演 | 田尻英三「インドネシア語・日本語の類義語の対照研究試論」 |
| 1990年度福岡大学日本語日本文学会 | |
| 期日 | 1990年11月24日(土) |
| 会場 | 福岡大学セミナーハウスAセミナー室 |
| 講演 | 山本哲也「言葉と表現」 |
| 福岡大学日本語日本文学会 〒814-0180 福岡市城南区七隈8-19-1 福岡大学人文学部日本語日本文学科気付 ℡ 092-871-6631(代表) FAX 092-871-6654 E-mail nichibungakkai*fukuoka-u.ac.jp (*を@に置き換えて送信してください) |